記事更新日:2024年06月25日 | 初回公開日:2024年06月25日
用語集 グローバル用語解説 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報

アカハラとは、教育の場で権力を利用して不当な言動を取るハラスメントです。アカハラとは、アカデミックハラスメントの略で大学や高校などの教育現場で主に起きています。力関係がある立場で発生するハラスメントに一つで、指導や監督を行う立場の人が逆の立場の人に対して行う嫌がらせ行為などを指します。教員から学生や指導員から研究員などに対して行われることの多いアカハラですが、教員同士や学生同士で行われる場合もあります。

アカハラと似た物に、パワハラがありますが2つは嫌がらせが起こる場所が異なります。アカハラは教育の現場で起きるのに対してパワハラは職場全体のハラスメントが含まれています。パワハラが問題になっている企業も少なくないため、耳にしたことがある人も多いはずです。アカハラとパワハラともに、力関係がある立場の人が嫌がらせやいじめを行うという点は同じです。パワハラに関しては、労働にあたって防止措置の努力義務が科せられるようになりましたが、アカハラも対応が求められています。

アカハラが問題視されているのは、教育機関への不信感が強まるからです。アカハラが行われている教育現場では、教育や研究の場において健全な関係性が築かれていません。そういった環境では被害者の精神的健康やアカデミックキャリアに大きな影響を与えてしまう恐れがあります。アカハラが行われていると学内の信頼関係を壊し、教育機関への不信感を増大させてしまう可能性もあります。学問の自由や生徒の創造性を奪ってしまうことにも繋がりかねません。

アカハラの具体例として、学習や研究を妨害することが挙げられます。学習を行う上で必要なデータや機器の貸出を行わない、研究テーマを与えずに雑用をさせる、学会への参加を拒否するなどがあげられます。教育機関において学生が学習・研究を行うことは学生の持つ権利ですが、理由をつけて学習や研究を妨害することは権利侵害です。研究室などは閉鎖的であることが多く、アカハラが起きていても表沙汰にならない場合が殆です。また実際にされていても、相談できないということも多くあります。
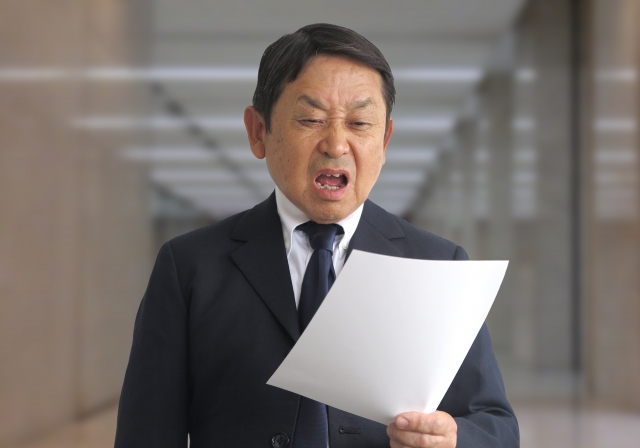
アカハラは、進級や卒業を妨害する行為も含まれます。推薦に十分な成績を収めているにも関わらず推薦状を書かない場合や、不当な理由で進級や卒業を妨害するといった行為が該当します。進級や卒業は学生の人生を大きく左右する出来事です。理系を希望している学生に文系を勧める、卒業するのに十分な成績や単位を収めているにも関わらず卒業を妨害するなどもアカハラになります。留年の強要や卒業論文の不当な評価も教授の裁量で判断されているため、アカハラが起こりやすくなります。

アカハラの一つとして、就職活動の妨害もあります。専門的な研究を行っている場合などは、教授の推薦状を元に就職活動を行う学生も少なくありません。しかし推薦状などは教授の裁量に任されている部分も多く、特定の学生を贔屓する等といった事象が起きやすくなります。他にも就職に必要な情報を与えない・企業に圧力をかけて内定を取り消すなど学生に不利益を被るような行動も全てアカハラです。望んでいない就職先を斡旋することも、アカハラに該当します。

アカハラは教育や指導を疎かにすることもあります。正当な理由なく講義を行わない・放任主義や必要なサポートを行わずに放置することがあげられます。教育や指導を放棄することは、直接何かをされることよりも分かりづらいためアカハラと認識していない人も少なくありません。教育や指導を行う事は、教育機関に所属している上で義務となっているため必ず実施しなければなりません。それにもかかわらず指導者が教育に対して怠慢な態度や消極的な態度を取っている場合は、アカハラと言えます。
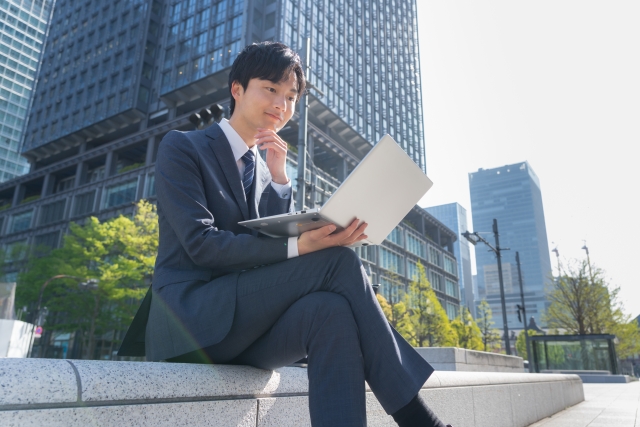
研究成果やアイデアを盗用するのも、アカハラです。学生が書いた論文やアイデアを自分の論文などとして発表する・論文に貢献した学生の名前を載せない、論文に名前を乗せる順番を好みで決めるなどが当てはまります。指導する立場を悪用して、学生のアイデアや論文を自分のものにする事が該当します。また単位がほしければ論文の第一著者に教授の名前をいれるように脅すこともアカハラです。盗用などは著作権侵害の問題に発展する恐れもあります。

経済的な負担を強要するのもアカハラといえます。経済的な負担とは具体的に、研修に必要な費用を学生に出させる・研究費用から支出すべき費用を学生に払わせるなどがあります。他にも、実験に失敗した場合などに学生に支払いを矯正させるのもアカハラです。また卒業論文に必要な実験器具や物品などは、研究室などで購入する様になっていることが一般的ですが、そういった支援を行わずに自腹で購入させようとするのも立派なアカハラになります。

プライバシーに介入してくるのもアカハラの一種です。学生の個人情報を勝手に他人に教えることや、スマホの中身を見せるように強いる・成績を許可を得ることなく開示するなどが該当します。他にも研究時間以外に執拗に連絡を行う・ゼミの時間以外に拘束し雑用をさせるなどもプライバシーに介入しているアカハラです。指導や研究に必要のない個人情報を詮索する行為や、本人の許可を得ることなく個人情報を他人に流す行為はアカハラだけでなくプライバシー侵害にもなります。

大学で実際に起ったアカハラは、教授が不適切なメールを学生に送った事件です。大学の准教授が学生に向けて誹謗中傷や暴言などを多く送りつけており、中には脅迫めいた内容のものも含まれておりアカハラと判断された事例です。このアカハラに対して大学側は、その准教授を減給処分としました。この処分は不当だとして、准教授側が裁判を起こしましたがメールの内容から立場の弱いものに対しての威嚇的で脅迫めいた内容が多く送られていることから、処分は有効であると判断されました。

アカハラが起こる原因は、閉鎖的な環境が影響しています。大学や研究室は高校や中学と異なり、閉鎖的な環境になっています。研究内容などの機密情報が外部に漏れないようにするため、限られた人しか出入りができない研究室などもあります。また理系の研究室は研究をチームで実施しているため縦社会が起こりやすい傾向です。また卒業後の進路など教授の影響が大きく、研究室を離脱してしまうとその後の人生に大きな影響を及ぼす可能性が高いためアカハラが起こっていても中々離れられない環境になっています。
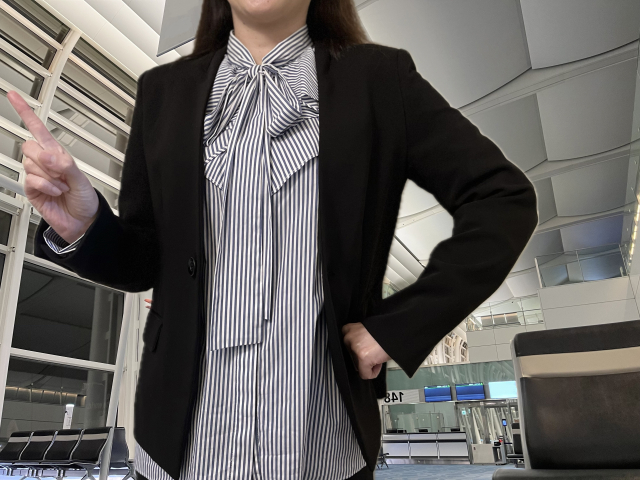
アカハラは、教授の権力が大きいため起こりやすいと言えます。大学や研究室では人間関係がピラミッド型で構成されており、トップの権力が絶大と言えます。権力がトップや上位に集中しているため、下の人は従わざるを得ない環境になっておりハラスメントが起こりやすい状況が出来上がっています。立場の弱い人が意見するとその後の指導や研究の障壁になってしまうことから、アカハラを受けていても中々申告することが出来ません。アカハラが起きていても、表面化しづらい要因とも言えます。

アカハラへの対策方法は、相談窓口を設けることです。アカハラは閉鎖的な環境の中で表面化することが難しく、被害を受けていても黙認している可能性があるため外部から観察していても実態を掴むことは出来ません。そのため被害を受けている学生が相談しやすいように、構内に相談窓口を設置するようにしましょう。相談窓口を設置する場合は、被害者の特定ができないように匿名やメールなどで気軽に相談できる環境を作ることが大切です。また相談員は人数を絞って情報漏洩などが起こらないように注意しましょう。

アカハラは、定期的な調査を行う事で対策することが出来ます。アカハラは研究室や講義などの小さな場所で起こっていることが多く、大学側が把握できていないだけで水面下で起こっている場合があります。水面下で行われているアカハラを顕在化するためには、定期的に調査することが重要です。大学側が動くことで、自分からは被害を訴えることの出来ていない学生を救うことが出来ます。調査を行う際は、被害を受けていることが加害者や他の人にバレないようにする匿名性を確保することが大切です。

アカハラを対策するには、外部の専門機関を利用するようにしましょう。大学内で相談窓口の設置や相談員を設けることが難しい場合は、外部のカウンセラーやNPO団体などと連携出来るようにしておく必要があります。専門知識を持っている人に相談できる環境が整っていれば、第三者ということもあり学生が相談しやすくなります。また相談窓口を構内に設置している場合も、外部機関と連携しておくことで公平な対応を取ることが可能です。学生が相談しやすい環境を提供することが大切です。

アカハラに対する理解促進を行うことも、アカハラの対策法です。アカハラを行っている人は、アカハラであることを自覚せず無意識のまま行っている場合もあります。自覚のないアカハラを防ぐためには、職員全員に対してアカハラを理解してもらう必要があります。アカハラを理解してもらうためには、定期的にハラスメント研修を実施することやガイドラインをわかり易い場所に掲載するなどの方法があります。アカハラについて理解してもらうことで、未然にアカハラを防止することが可能です。

アカハラの具体例やアカハラが起きる原因・対策方法などについて解説しました。アカハラは明確な規定が法律で行われておらず閉鎖的な環境にあるため中々表面化することが難しいハラスメントです。力関係によって生じるハラスメントのため教授から学生に対してだけでなく、上級生から下級生などにも起こりやすいと言えます。アカハラを防止するためには、大学や研究機関に勤めている人がアカハラをしっかりと理解する必要があります。アカハラに対する対策や周知を行い、学びやすい環境を整えていきましょう。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。