記事更新日:2023年04月11日 | 初回公開日:2023年04月10日
採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 グローバル用語解説 用語集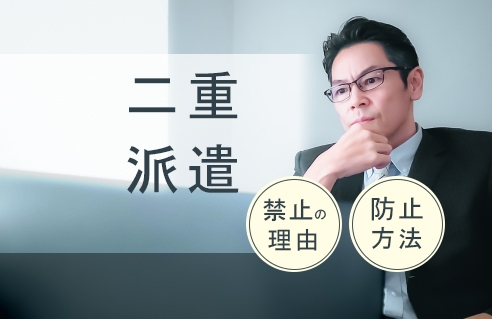

二重派遣とは、派遣されてきた従業員を別の企業に派遣することです。通常の派遣は、派遣される労働者と派遣元である企業が雇用契約を締結し、派遣社員は派遣先の指揮命令で業務を行います。派遣先で業務を行っていますが、雇用契約は派遣元と締結している為、給与支払いなどは派遣元の企業で行われます。しかし二重派遣は、雇用契約を結んでいない派遣社員を更に別の企業へと派遣する行為になり、労働者供給に当たり法律で禁止されてる行為です。

二重派遣が禁止されている理由は、労働条件が守られない可能性があるからです。雇用契約を結んでいる派遣会社と派遣社員の間には、勤務時間や業務内容・休日についての雇用契約が締結されています。これは派遣先と行う派遣契約の内容にも記載がされており、派遣先の企業でも契約内容に沿った業務や指示命令を行うのが通常です。二重派遣では、契約関係にない企業がスタッフへ指示命令を行う為、勤務条件や業務内容が全く異なる場合があります。

二重派遣の禁止は、雇用に関して責任の所存が不明確になることが理由の一つです。二重派遣によって、派遣社員は本来働く企業ではない場所で就労を行っています。様々な企業を介している事により、派遣社員に対しての責任は何処が負うのかが曖昧になってしまいます。責任の所在が曖昧になってしまうと、適切な賃金の支払いや労働者の雇用を守るという義務を企業間で押し付けあうといった事態にもなりかねません。そうなってしまうと労働者の保護が行えない為、二重派遣は禁止されています。

二重派遣は、中間搾取を防止するために禁止されています。中間搾取とは、労働者と雇用契約を締結する使用者の間で直接行うべき雇用契約に介入して、どちらかから謝礼を受け取ったり賃金の一部を先取りすることです。派遣社員が派遣元ではなく、雇用契約を結んでいない派遣先から指示命令を受けることも中間搾取に該当します。再派遣の場合には、紹介手数料を得る企業が増える為、派遣社員の給与が下がってしまい労働者の不利益に繋がります。

不当解雇が起きやすくなる為、二重派遣は禁止されています。派遣法に基づいている正しい労働者派遣では、雇用契約がしっかり締結されている為責任の所在が明らかになっています。しかし、二重派遣では責任の所在が明確になっていない為、派遣先企業から派遣されている従業員を不当に解雇しても責任を問われることはありません。こういった状態から、二重派遣では契約解除や不当解雇などの派遣切りが起こりやすくなってしまいます。

二重派遣が無くならない理由の一つに、取引先との力関係があることが挙げられます。企業を運営していく上で、取引が欠かせない上位取引先から従業員の派遣を依頼された場合、断るのは簡単ではありません。断ってしまうと今後の取引に影響が出てしまうのではと考え、要望に応じてしまいます。人材を派遣することは厚生労働省の許可がないと違法になりますが、上の立場に当たる企業から人材の派遣を依頼されてしまうと断り辛い為、二重派遣が無くならない実態があります。

人手不足により派遣労働者の管理が疎かになっている為、二重派遣が無くならない事が考えられます。企業規模に関わらず、人材の確保に苦戦しています。大企業では人事部などの部署に人員が確保されている為、派遣社員をきちんと管理することが可能です。しかし人員が限られている中小企業では、人事の専任担当者が置かれている事は珍しく兼務している事が多い為、しっかりと管理・把握することが難しい企業も多くあります。日々の業務に追われていると、派遣労働者の管理が疎かになってしまい二重派遣が起こってしまう可能性があります。

二重派遣を行った際に、職業安定法第44条において労働者供給事業へ抵触した場合、罰則が科されることがあります。労働者を派遣して事業を行うには、派遣会社と派遣社員の間に雇用契約関係にある必要があり、厚生労働省の許可が必要です。その為、この行為は労働者供給ではなく派遣事業に該当し適法と言えます。しかし二重派遣では派遣元とは雇用契約がありますが、派遣先がまた別の会社に派遣することは雇用関係がなく、労働者供給に該当する為罰則の対象となります。
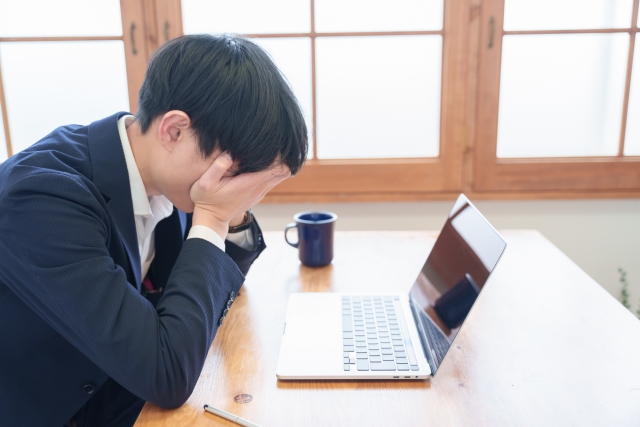
労働基準法第6条では中間搾取を禁じている為、二重派遣を行うと罰則があります。雇用契約を締結している企業と労働者の間に、第三者が介入し手数料などの利益を得ることを防ぐための法律です。有料職業紹介事業は法律に基づいて許可されており、労働者派遣事業は派遣会社と労働者の間に雇用契約を締結している為、中間搾取には該当しません。労働基準法に抵触すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

二重派遣であることを知らずに、派遣社員を受け入れた場合には罰則の対象にはなりません。故意ではない場合は、職業安定法や労働基準法に違反していない為、違反には該当しません。しかし、二重派遣であることに受け入れた後に気づいたにも関わらず、報告など行わないまま雇用を続けていた場合は、処罰の対象となります。処罰の対象にならない為にも二重派遣であることが判明した時点で、所轄の労働局などに報告をしきちんとした対処を行うことが大切です。

二重派遣を行い職業安定法違反第44条違反として罰則を受けるのは、派遣された人材を受け入れた後に派遣を行った企業とその派遣を受け入れた企業です。職業安定法違反第44条の違反は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。そして労働基準法第6条の違反の対象となるのは、派遣社員を再派遣を行った派遣先企業です。労働基準法第6条に違反すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されます。労働基準法には両罰規定が設定されており、二重派遣を行った事業主だけでなく関わった全ての人が処罰の対象です。

派遣先企業の人が、派遣労働者に対して指揮命令を行う請負や準委任で業務を行っているケースは二重派遣に該当しません。請負や準委任の契約は業務委託契約と同様に、決まった一定の内容の業務を個人または他の企業に委託することを言います。請負契約は業務を請け負った人が完遂させ、その成果に対して依頼主が報酬を支払います。準委任契約は、知識や技術を持った人に対し決められた期間の間、依頼者の業務をサポートする契約です。請負や準委任は、依頼者から直接指揮命令を行う権利はありません。
出向先で別の会社に出向させるケースも二重派遣には当たりません。出向とは、企業が対象の従業員と雇用契約を維持したまま関係企業などで業務に従事させる方法です。従業員の籍は元の企業にあり、給与の支払いなども出向元の企業が責任を負いますが、指示命令は出向先で行われます。通常の派遣と似ているように思えますが、出向は出向先の企業とも労働契約があるのに対し派遣は派遣先企業と労働契約がない点が異なります。出向先との企業とも労働契約が交わされている為、出向先で別の企業に更に出向させても二重派遣には該当しません。

二重派遣を防ぐために企業側は、定期的に勤務実態を確認するようにしましょう。派遣契約を締結していても、契約後に確認した雇用条件とは異なっている場合もあります。そうならない為にも、定期的に派遣社員に対して異なる勤務実態になっていないか、誰から指示命令を受けているのかなど確認を行いましょう。ヒアリングを行う際は、派遣社員に不利益が発生しないよう注意が必要です。派遣社員へのヒアリングだけでなく、実際に行っている業務の現場をチェックしたり人事に確認したりすることも有効です。
二重派遣は、派遣社員を直接雇用することで防ぐことが出来ます。正社員雇用の人が関係企業に出向いて業務を行う出向とは違い、派遣社員は派遣元の社員ではない事が多い為、関係性がどうしても薄くなってしまいます。結びつきが薄い分、どうしても二重派遣などのリスクが高くなってしまいます。優秀な派遣社員を自社関係先や取引先に派遣したいと考えている場合は、受け入れている派遣社員と直接雇用契約を締結しましょう。自社の社員として関係先に送り込むことは二重派遣には該当しない為、方法の一つと言えます。

二重派遣されない為にも、労働者は契約内容をしっかりと確認しておきましょう。契約内容には、指示命令系統なども記載されています。指示命令系統がきちんと派遣元になっているかを確認し、違う企業が記載されている場合などは確認することが大切です。派遣先で就業を始めた後も、指示は何処から来ているのかを確認しておくことも重要です。事前にしっかりと把握しておくことで、自分の身を守ることが出来ます。二重派遣に巻き込まれないようにするためにも、意識を高く持っておきましょう。
二重派遣に巻き込まれないように、派遣会社を選ぶときは信頼性の高い会社を選ぶようにしましょう。よく知られている大手企業は、コンプライアンス対策などがしっかりしている為、二重派遣が発生しにくくなっています。登録者も少なく、あまり聞いたことが無いような派遣会社では管理体制が整っていない場合などもある為、二重派遣に巻き込まれてしまう可能性があります。大手派遣企業は、登録者数も多く口コミが書かれていることもあります。事前にチェックし、信頼できそうな派遣会社を選ぶようにしましょう。

二重派遣の罰則や、二重派遣を防ぐための方法について解説しました。二重派遣は派遣スタッフ保護の為にも禁止されている行為です。二重派遣になってしまわない為にも、企業側は派遣会社に任せたままにするのではなく、雇用関係や契約内容などをしっかりと確認することが大切です。知らないうちに二重派遣になっている派遣社員を受け入れていた場合は、見て見ぬふりをするのではなく然るべき対応を取りましょう。二重派遣は企業としてのイメージダウンに繋がります。しっかりと理解し、定期的に注意をして予防しましょう。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。