記事更新日:2022年11月11日 | 初回公開日:2022年11月11日
用語集 外国人採用・雇用 グローバル用語解説 人事・労務お役立ち情報
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。

kptとは、仕事内容を3つのステップで振り返ることです。日頃の業務やプロジェクトにおいて、「振り返り」を行うことは今後の業務の生産性向上へと繋がります。業務改善のフレームワークとしてkptが存在しています。kptは「Keep(成果が出ている為継続を行う)」「Problem(問題が発生しており改善が必要)」「Try(新しく取り組みを行う)」という順番で検討を行います。それぞれの頭文字からkptと呼ばれています。kpt法を活用することにより、項目が整理され何をすべきなのかを明確にすることが可能です。

kptの目的は、課題の共有と改善点の明確化を行うことです。kptは業務の振り返りを行うには効率的な手法です。シンプルな手法なので、振り返りは1人でも大人数でも活用可能です。業務を行う上で、チームとして動く場合、営業や開発・エンジニア等様々な職種の人で構成されます。同じチームだとしても、職種が異なる場合は業務内容や目標などは分かり辛く課題の共有等も難しくなります。kpt法を用いることで、職種関係なく課題の共有やチーム内の改善点などを明確化することが可能です。

kptを行うタイミングは、プロジェクトが一段落した際が最適です。プロジェクトが終わり、出来るだけ期間を開けずに行うことで進め方などを明確に記憶しており、振り返りによって得られる質も変わってきます。プロジェクトが一段落した後だけではなく、週や月毎にkptを行うスケジュールを事前に決めて実践することも大切です。他の会議などと同様に、業務の一環としてkptを行うことを従業員に習慣づけることにより業務の質向上を図れます。kpt法を適宜実施している場合にも、プロジェクトで何か問題が発生した場合は随時実施するようにしましょう。
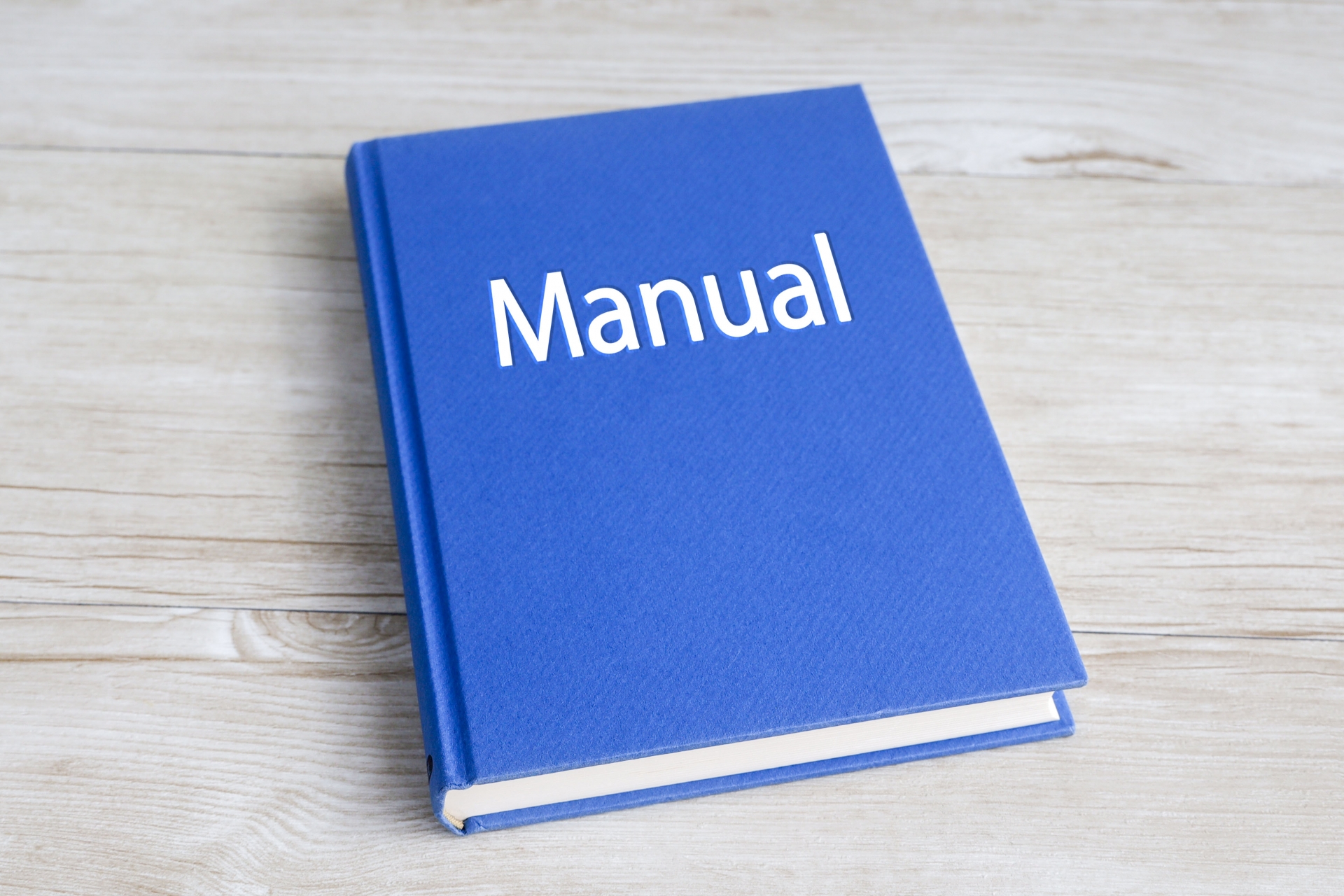
kptを実践する際には、ルールとフォーマットの準備が欠かせません。ルールやフォーマットは自社に合わせ、使いやすいものを作るのが1番です。一般的な例として挙げると、ホワイトボードを用意し中心に縦線を入れ左側にはKeep(継続・良い点)とProblem(問題点)を記載し右側にTry(挑戦予定・工夫する点)などを記載していきます。ルール設定では、「振り返りに集中し、積極的に参加する」「人の話を遮らずに一人で話をしない」といったあまり難しくないルールを決めましょう。チームの状況により、話し合いながらルール決めを行うことが大切です。

フォーマットやルールを決めたら、KeepとProblemの内容を付箋に書きましょう。Keepには業務で上手く行ったことや、良かったことを書き出します。Keepの書き出しを行う際には、一緒にkptを行っている人達とはなるべく会話をせず書き出しを行いましょう。他の人と話してしまうと、他人の思考に影響される可能性もあります。洗い出しが終わったら、チーム内で意見交換を行いながら貼り付けることでチーム内の一体感も高まります。Problemも同様に行っていきましょう。

KeepとProblemを付箋に書き出した後は、それぞれで書き出した内容についてディスカッションを行いましょう。付箋に書かれている内容に対して、コメントや意見を参加者全員からヒアリングし、議論していきましょう。付箋に記載した理由や、問題となってしまっている要因などをチーム内で掘り下げることが大切です。良い点を更に向上させる話し合いも重要ですが、KeepよりもProblemが多い場合にはProblemを中心に話し合いを行う必要があります。問題点も優先順位などを付けて重要度が高いものから話し合いましょう。

問題点などを話し合った後は、具体的なアクションを考えていきましょう。参加者に記載してもらったTryの項目に対して、どういったことを行っていくのか話し合う必要があります。具体的である必要があるので、「○○を頑張る」等と言った抽象的にならない様注意しましょう。Tryの項目が多い場合には、KeepとProblemの議論同様に優先順位を付けて議論をしていくことが大切です。次回以降のkptを行う際にTryを行った結果や進捗状況を確認し、改善を繰り返し行っていきましょう。

kptを行う上で、意見を出しやすい雰囲気を作ることが大切です。参加している人から様々な意見を出してもらうためには、思いついたことを発言しやすいルール作りや運用が欠かせません。KeepとProblemの洗い出しを行う際には、出た意見に対して批判を避けることにより様々な意見を集めることが出来ます。言うまでもないことと思っている場合でも、その意見が企業にとって貴重な考えである場合もあります。kptでは深く考えずに様々な意見を発言できる様な、雰囲気作りが重要です。

kptは枠に捉われずに意見を広げることが、実行する上でポイントとなります。枠を作ってしまうと、その枠にばかり気を取られてしまい参加者からの意見が少なくなってしまう可能性があります。意見が少なくなると、kptを効率よく行っていくことが困難です。枠に捉われないようにするためには、あらゆる価値観を受け入れましょう。価値観を否定してしまうと、従業員の人格そのものも否定することにもなってしまいます。意見を否定された従業員が発言出来なくなってしまうことは避けなければなりません。

kptを行う上でのポイントは、期間を決めて繰り返し行うことです。定期的にkptを実践することで、アクションプランがしっかりと運用できているか確認することが出来ます。アクションプランが上手く回っている場合はKeepの意見が増え、上手く回せていない場合にはProblemの意見が増えます。定期的にkptを行う時には、kptを行う内容により実施頻度を変更しましょう。効果をより発揮させることのできる頻度を見つけ、kptを実行していく必要があります。また、前回のkpt内容と比較することでよりkptの質を高めることが出来ます。

kpt実践に役立つツールに、KPTonがあります。KPTonとは、コロナなどの影響でリモートワークを行っている従業員が多い場合でも、オンライン上で意見交換が出来るツールです。kptを効率よく行うための機能がいくつも搭載されており、無料で利用出来る為コストを抑えたい企業にもピッタリです。個人で考えをまとめる為のホワイトボード機能や、参加者全員が閲覧できるホワイトボード機能等用途に合わせて活用することが出来ます。kptの段階に合わせた使用が出来、全快実施した内容等も照らし合わせられるため、改善を行いやすくなっています。

スプレッドシートもkpt実践に役立ちます。スプレッドシートは、Googleが無料で提供している表計算ソフトです。公開範囲を設定出来る為、個人でもチーム全体としても活用することが出来ます。クラウド上で自動保存されるので、いちいち保存する必要もありません。使用法はエクセルと変わらない為、枠決めを行えばパソコン上でkptを行えます。kptを行った度にシート分けを行うことで、時系列で振り返りの内容の確認も出来ます。使い方は様々あり、kptのやり方に合わせて用途を変えることが可能です。

kptを実践するには、Miroを活用しましょう。Miroは900万人以上が利用している、デジタルホワイトボードです。様々なグローバル企業でも活用されています。Miroでは日々の業務やプロジェクト内で続けることや業務課題・挑戦すべき事を付箋で登録し、「Board(ボード)」で管理を行います。Boardは複数の利用者が同時に編集を行うことができ、スプレッドシートやドキュメントの埋め込みも可能です。チーム課題や目標の共有化だけではなく、オンライン会議の議事録等の機能もあるのでkptを実施するには最適のツールです。

kptを活用すると、課題の早期発見に繋がります。kptでKeepやProblemの洗い出しを定期的に行うことで、業務においても俯瞰して自分の行動を分析する習慣や力が身に着きます。kptを行う回数が増えるほど、業務や活動の内容に向き合う時間が増えて問題を早期発見することが可能です。問題が大きくなる前に気づくことが出来れば、すぐに修正を行うことが出来ます。kptを活用しチームで課題を共有することで、従業員各自で迅速な対応を行うことも可能です。

kptは組織の一体感が向上するメリットがあります。kptでそれぞれの意見交換の場を設けることで、従業員が考えている課題や考えなどの摺り合わせを行うことが出来ます。お互いの認識を合わせることが出来る為、チームが同じ方向を向けるという点もメリットです。課題や問題の洗い出しを行うProblemだけではなく、プラス要素となるKeepや新しい挑戦Tryに置く目標も重要です。問題点がある現状をしっかりと受け入れ、今後のモチベーションを高めるような運用を行いましょう。

kptを活用することで、次に取るべきアクションが明確になります。KeepやProblemでの現状把握を行うことで、Tryで次にするべき事をしっかりと決めることが出来ます。問題点などを共有することによって、kptに参加している全員が何故次にそれをするべきなのかという目的意識も芽生えます。目的を共有することによりチームの一体感を高めることが可能です。チームの一体感が高まると、コミュニケーションが活発になり新しいアイデア等も出しやすくなり組織としての生産性も高まります。

kpt実施において役立つツールや、実施する際のポイントについて解説しました。しっかりと振り返りを行うには、参加者全員が発言しやすい雰囲気を作ることが重要です。発言しづらい雰囲気では効率よく改善を行えません。kptのルールを作る際にも、細かく決めるのではなく大まかに決めておくことでルールに縛られずに実行することが出来ます。参加者一人ひとりが当事者意識をもって振り返りを行い、改善案を提案できるような運用を行っていくことが大切です。kptを活用して、振り返りを効果的に行いましょう。
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。