記事更新日:2020年10月30日 | 初回公開日:2020年10月22日
人事・労務お役立ち情報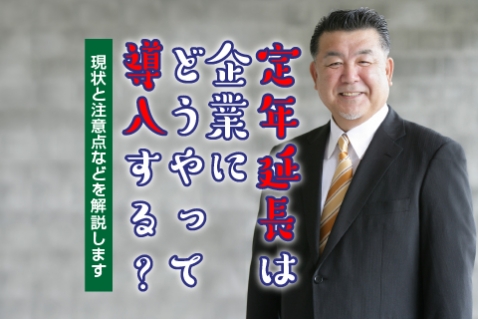

定年を60歳に定めている企業が「高年齢者雇用確保措置」(雇用確保措置)に基づき60歳以降に65歳に到達するまで、希望者すべてに雇用の保証を行うことです。同法の具体的な方法は3つあります。
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止(定年制の廃止)この3つが「定年延長」となります。
ただしこれは2021年3月までとなり、2021年4月からは改正法での適応となります。この背景には厚生年金の引き上げがあり、段階的に受け取れる年齢が引きあがります。これにより収入がない時期を防ぐ措置となります。
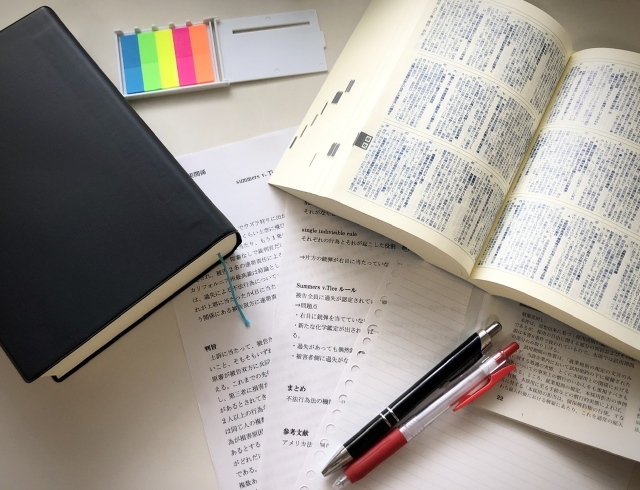
2021年4月の改正では新たに2つの項目が加わり、定年が70歳まで引き上げられます。新しくなるものと改正させるのか以下の通りです。
上記に加え、他企業への再就職支援・社会貢献活動参加への資金提供・起業支援・フリーランス契約への資金提供が努力義務となります。

2025年には全人口の5人に1人あたりが75歳を迎え、65歳以上の高齢者は3人に1人の超・高齢化社会を迎えます。高齢者の「雇用の確保」や「再就職の促進」を目的とし、経済・社会発展への寄与も期待されています。将来的な労働力を確保するために定年延長の制度が施工しました。現在の高齢者は働く意欲も知識もあり、2021年に施工される法律では企業支援も受けられる事となります。新しい会社の設立やフリーランスに転身する高齢者も現れるかもしれません。

企業にとって指導者の育成は目下の課題と言えます。定年延長の制度を利用して、シニア社員の知識を若手社員に教育することで、指導者育成の課題が解決するが場合があります。ベテラン社員の残留により現場力を保持したまま、若手社員の育成に力を発揮させることでシニア社員のモチベーションが上がることが期待されます。継続雇用した場合、人材確保で広告費を抑えられ、雇用の管理のしやすさもメリットと言えます。教育時間と経費を抑えられる選択肢に加えてもいいかもしれません。

定年を延長して勤務する際は再契約を結ぶ必要はありません。面談で本人の希望条件をしっかりとヒヤリングした上で雇用継続を行いましょう。継続雇用の場合、社員は大幅な減給がなく現在の業務を継続的に行うことができます。しかし委託社員やパートに雇用形態を変更する際は雇用契約が必要になります。雇用契約の変更は給与の減額や昇進条件が変わります雇用契約の変更は給与の減額や昇進条件が変わります。雇用契約を変更しても、業務の維持が可能となるため組織への影響はなく業務遂行がスムーズに行えるでしょう。

退職を望まず、業務継続であれば給与の大きな減額は難しいと言えます。また賞与・退職金も何の措置もしなければ変わりません。そのため人件費の減少は期待できず、新人の採用や新規事業等への割り当てが難しくなるでしょう。そのため企業の若返りと事業開発が思うように進まないかもしれません、また多少の減額となる場合も社員のモチベーション維持をどう保つかが課題となってくるでしょう。人件費の削減は難しいかもしれませんが、助成金制度があるので活用してみてはいかがでしょうか。

再雇用契約の場合、就業条件が変化する場合があります。就業条件が変化すると給与体系も変化し、給与が減額する可能性があります。給与の減額になると、賞与・失業保険の減額にも繋がります。また退職金も5年先延ばしになり、モチベーションの維持が難しくなる可能性があります。シニア社員は健康維持も課題となり、ライフスタイルの変化をもたらすかもしまれません。働き方が変わるとライフプランの変更や、体調が崩れがちになる変化も企業は考えなくてはならないのかもしれません。

厚生労働所の調べでは約80%の企業が導入している継続雇用ですが、大手企業より中小企業が多く導入しているようです。就業条件が変わらず、賃金も変わらないため退職金は65歳での付与となります。また、再度契約を結びなおす必要がないので再契約の手続きや就業条件の話し合いがないので時間の負担は最も少ないと言えます。この場合有給や手当も変わらないので、社員のモチベーション維持には最も効果的となり、65歳まで安定して仕事ができます。ただし、退職金が60歳で貰えないことと業務への負担はあるかもしれません。健康状態を維持しつつ、業務遂行をできるように企業も社員に対しての仕組みづくりが必要かもしれません。
定年延長では、雇用を結びなおす再雇用の導入は大きなメリットと言えます。雇用形態の見直しで社員の業務内容を変更したり、時間短縮を図り人件費の削減もできます。この場合の社員のメリットは、健康やライフスタイルの見直しになり、継続的に安心して働くことができます。退職金も60歳の時点でもらえるので、モチベーションも維持しやすと言えます。契約期間を1年ごとに契約を更新するフルタイム有期雇用契約社員(嘱託社員)を導入している企業もあります。
企業全体の2.6%と導入している企業がかなり少ないですが、定年廃止での業績が伸びた会社もあります。定年廃止なので業務形態は変わらないのですが、全社員に対しての業務形態変更が必要かもしれません。就業開始終了の時間を見直し、実際の就業時間を短くするのもいいかもしれません。退職金制度を導入しないため、賃金や賞与も考慮する対象となります。毎月の賃金に上乗せや退職金を自分で管理する仕組みづくりを考える必要があります。

上記の3つの選択肢がある中で、社員はどの働き方が将来的に自分に合うのかを確認する必要があります。また企業がどの定年延長の制度を導入しているかも確認しましょう。再雇用になる際は、「雇用形態」「賃金」「各種手当と有給手当」「契約期間」を確認しましょう。継続雇用では、給与・退職金減額になるある可能性があります。また健康面等での業務継続が可能かどうか判断しましょう。定年廃止では、年齢での働き方ではなくワークバランスやライフスタイルに合わせた働き方と賃金を確認しましょう。


3年に1歳ずつ引き上げられている雇用期間ですが、2025年には措置が完了予定です。そのため65歳までの雇用が義務化となります。また希望者を雇用できない企業は、指導や助言が国から入り、改善されない場合は会社名の公表も行われるようです。企業は社員をのコミュニケーションや仕組みづくりが措置期間終了までに間に合うようにしましょう。大手企業では1on1面談での社員の個性を尊重できるような仕組みづくりや、組織の意識改革に前向きな動きも見せています。

再雇用(契約社員等)を選択した場合は60歳で受け取れる退職金ですが、雇用継続の場合退職年齢により退職時に受け取れます。しかし、65歳での退職金の受け取りだと社員のライフプランを見直さないといけません。この問題の解消は退職金の打ち切り支給ができます。税制面では「相当の理由があると認められる場合」です。この場合は税務署や労務等の関係機関に問い合わせが必要となってきます。また継続雇用ですと、退職金の金額も従来通り積み増しになるのか、固定のままなのかを検討しなければなりません。

定年延長を希望する社員は継続しての雇用義務が発生します。これは60歳になる社員に対し、事前に通告をしている企業が多いようです。通告は、できれば個別の対応が望ましいでしょう。また、雇用形態の相談やライフプランを丁寧に聞き出せると、円滑に雇用延長ができるのではないでしょうか。ヒヤリングの際、業務継続や再雇用等の選択肢も提示すればお互いの合意までスムーズに手続きが可能となります。2025年の65歳定年制定までには、定年延長の3つの選択肢から企業に合ったものを導入したいですね。

先ほどお伝えしましたが、男女により退職の理由が分かれます。これをヒントに今後の雇用継続ができるのではないのでしょか。男性は賃金をネガティブに考えるため、賃金の低下は社員との相談が望ましいでしょう。また仕事に対する個別の対応が必要かもしれません。社内の業務変更や賞与・ボーナスなどの給与面への配慮が必要かもしれません。女性では健康面や自分のやりがいを外に求めているので、時間を短縮したり、社員の個性によりコミュニケーションを取れる部署に移動するのもいいかもしれません。

健康維持や少子化に伴い、人材確保は企業の課題となります。そのため定年延長は現場力の維持にとても効果的と言えます。2025年には高年齢者雇用安定法の施行は完了、65歳定年となります。さらに70歳定年の可能性もあるので、長期的かつ細かいコミュニケーションが必要になってくるのかもしれません。シニア労働者に対しての取り組みもそうですが、企業にいる社員の改革も見据えての導入が求められそうです。「長く働きたい」「「元気だからまだまだ働ける」シニアも多いので、定年延長を前向きに捉え、活用していきましょう。

「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
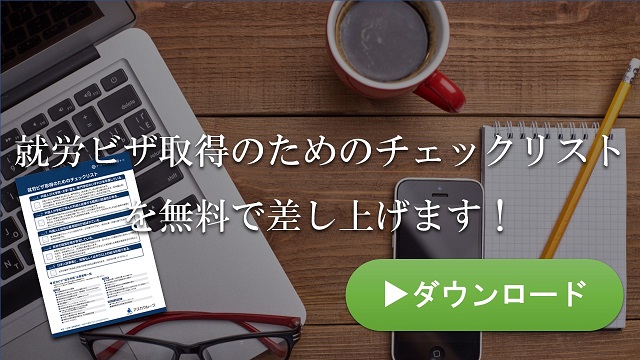
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。