記事更新日:2023年07月03日 | 初回公開日:2023年06月29日
用語集 外国人採用・雇用 グローバル用語解説 人事・労務お役立ち情報

相互理解とは、お互いの考えや立場を理解しあうことです。業務を円滑に進めていく為には、上司や先輩だけでなく同僚と相互理解しておくことも大切です。お互いを理解しているつもりでいても、依頼した内容と違う仕上がりになっている場合や依頼通りに業務を行ったのに評価されないと感じている事があります。そういった事態に陥っている場合、しっかりと相互理解が出来ていません。相互理解は表面上理解することではなく、相手の性格や思考など様々な事を理解することです。

相互理解は、コミュニケーションに変化が起きている事から注目されています。働き方改革やコロナウイルスの流行により、テレワークが広まりオンライン上でのコミュニケーションや管理に注目が高まっています。コミュニケーションの方法が変化している事により、従来よりも定期的に目標に対しての進捗を共有する仕組みや、情報共有する仕組みなども変化しています。進捗や情報共有をスムーズに行う為には、発言しやすい環境が欠かせません。相互理解を行うことでコミュニケーションの質を高めることが出来ます。

相互理解が注目されているのは、人材が多様化している事も影響しています。先進国の他の国と比べて遅れていますが、日本でもダイバーシティ化が推進されています。ダイバーシティ化を進めることにより、人種・国籍・文化など様々なバックグラウンドを持っている人材登用が進み、企業内での多様化が進んでいます。様々な背景や思考を持つ人たちが、同じ目標に向かっていく為にはお互いの思考や状況について理解することが重要です。

相互理解を行うことで、自律的にキャリアを考えることにも繋がります。従来までは、終身雇用制や年功序列などが重視されていましたが、雇用の流動性が高まり転職を行うハードルも低くなっています。その為、従業員は所属している企業でキャリアを形成を考えるのではなく自分の目指す将来や目標を自律的に考える人が増えています。企業の中で自律的に働くには、自己理解だけではなく上司や先輩から何を求められているのかを理解することも大切です。

マネジメントの方法が変化している事も、相互理解が注目されている理由です。働き方やワークライフバランスを重視している人が増えている影響で、マネジメントも従来の飲みにケーションや長時間労働が当たり前という方法では通用しません。従来のままのマネジメントを行ってしまうと、従業員のモチベーション低下や離職に繋がる可能性もあります。そうならない為にも、相手の立場になって歩み寄ることが大切です。相互理解を前提としたコミュニケーションを行いながらマネジメントをしていくことが重要です。

相互理解がしっかりと行えていないと、部門間の連携がスムーズに出来ません。同じ部署で働いている従業員同士は毎日コミュニケーションを取れる為、思考や行動についてある程度理解することが出来ます。しかし部署が異なる場合は、業務上かかわりを持つことはあってもお互いを理解するのは簡単ではありません。他部署と一緒に業務を行う必要がある場合には、部署内で業務の優先順位も異なり連携が難しくミスに繋がってしまう事もあります。思い込みなどから発生するミスを防ぐためにも、相互理解が大切です。
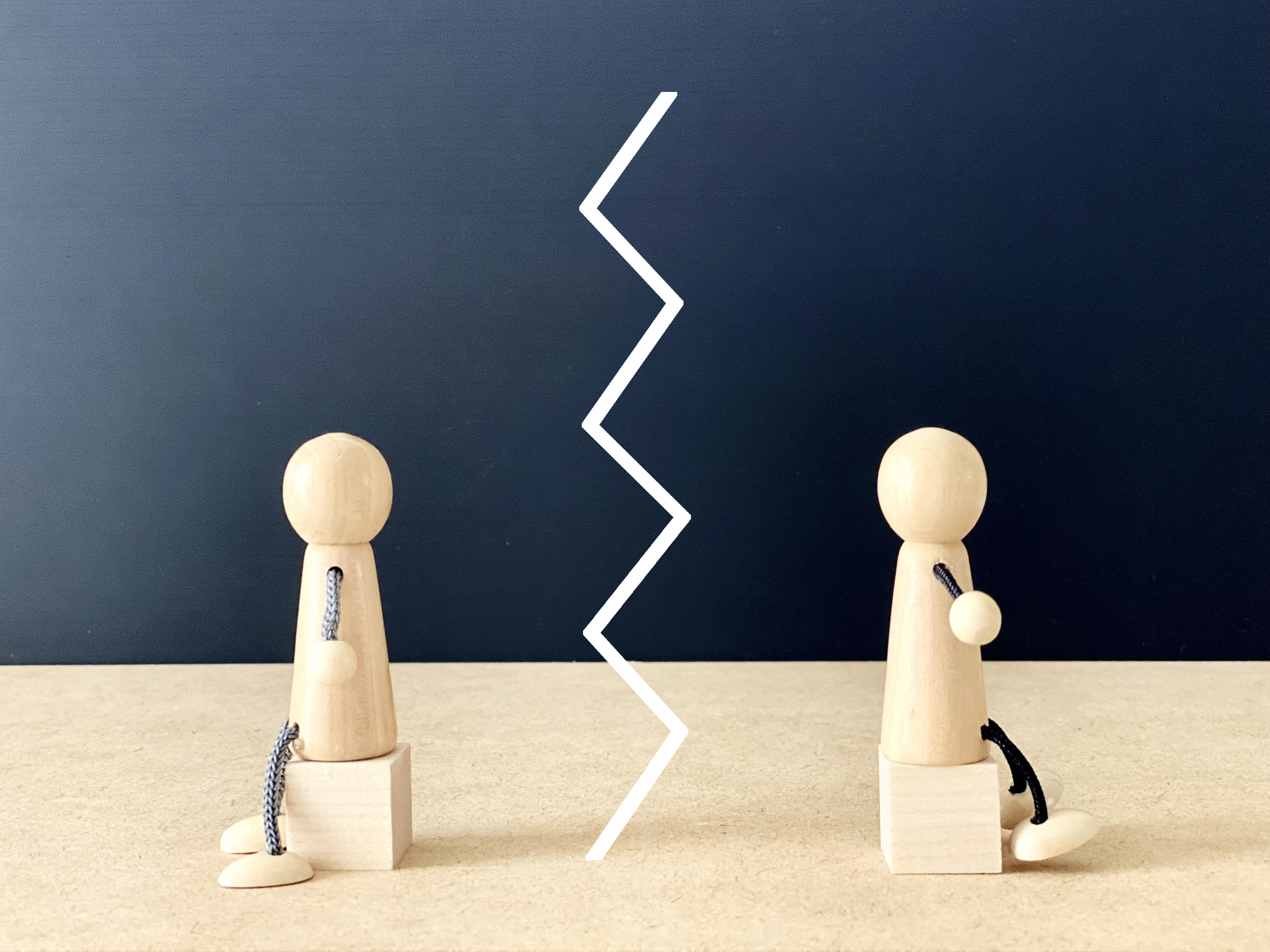
相互理解不足では、上司と部下の間に軋轢が生じる可能性があります。上司と部下の間で、お互いの事をしっかり理解出来ていない場合はお互いに溝が出来てしまうかもしれません。多い例として、部下はしっかりと業務に取り組み頑張っているのに上司から評価されないと感じる場合が多くあります。こういった状態が長く続いてしまうと、業務へのモチベーションが下がり心身のストレスに繋がりかねません。お互いに理解出来ていれば避けられる事態の為、相互理解が欠かせません。

チームでの仕事が上手くいかないのも、相互理解不足で生じる問題です。個人のペースで進めることが出来る業務には相互理解は必要ありませんが、チームとして取り組むプロジェクトはお互いの事を理解しておく必要があります。お互いを理解出来ていない状態で進めてしまうと、業務の優先順位に差異が生まれてしまい進行に影響を及ぼす場合もあります。相互理解が出来ているチームはしっかりと連携がとれている為、全員の力を合わせスムーズに業務を遂行することが可能です。

相互理解を深めることで、主体性を発揮しやすくなるメリットがあります。業務を行っていく上で、個人で業務を行う際にも上司への報告や同僚への共有は大切です。相互理解が深まっていると、上司や先輩・部下との信頼関係が構築されている為、報連相を行いやすい環境になっています。上下関係に捉われることなく積極的に相談することが出来、問題が大きくなる前に解決することが出来ます。意見を出しやすい環境ではコミュニケーションも活発になり、主体性を発揮しやすくなります。

心理的安全性が確保出来るのも、相互理解を深めるメリットです。部署内やチーム内で相互理解を深めることが出来れば、お互いの能力や思考をきちんと把握することに繋がります。上司が部下の事をしっかり理解することが出来れば、最適な目標設定や業務振り分けを行うことが可能です。自分のことを理解して貰えると安心感が生まれ、定着率を向上させる効果も期待できます。相互理解出来ている職場は安心して発言することが出来る為、心理的安全性に繋がります。

相互理解を深めるには、シャッフルランチを行いましょう。シャッフルランチは普段の業務で関わることが無い部署の人達とランチに行ってもらう制度です。業務から離れて、他の部署の従業員とランチをすることでオフィスでは話しにくい事やお互いの人柄について気兼ねなく話すことが出来ます。業務外なので、踏み込んだ話もしやすく仕事を行う前に信頼関係の構築にも繋がります。しっかりと工夫をしてランチを実施する事で、効果的な施策になります。

相互理解は、1on1ミーティングでも深めることが可能です。1on1ミーティングは上司と部下の2人で、個別ミーティングを行います。業務で困っている事や、現状抱えている不満など評価面談などの場で言いづらい事を引き出す場として活用されています。1on1はあくまでも部下の成長を促すための手段の一つなので、信頼関係を築く為には業務に関係ない会話も必要ですが雑談ばかりにならないよう注意しましょう。上手く活用することで、相互理解を深める事に繋がります。

相互理解を深める方法は、ゲームやワークショップを行うことです。働き方改革やコロナウイルスの影響で、出社せずテレワークを実施している企業も増えています。対面で顔を合わせていた時と比べ、テレワークでは中々コミュニケーションが取り辛いことから、従業員が打ち解ける為にゲームやワークショップを取り入れられています。人狼ゲームや謎解きゲームを活用することで、お互いの考え方や特性について理解することに繋がりゲームをしたことでコミュニケーションを取りやすくなります。

フリーアドレス制度の導入も、相互理解を深めることが出来る方法の一つです。フリーアドレスは、従業員が座る座席を固定せずに空いている場所に自由に座ってもらう方法です。フリーアドレスを取ることで違う部署の人とも触れあう機会が増え、相手が行っている業務への理解やコミュニケーションが取りやすくなるメリットがあります。チーム外の人とコミュニケーションを取ることで、従来の座席では生まれなかった繋がりが生まれ、相互理解に繋がります。

ジョブローテーション制度を活用して、相互理解を深めて行きましょう。ジョブローテーションでは、数か月から数年の単位で働く部署や職種が定期的に変わります。様々な部署で業務を経験することにより、今までは関わりがなかった部署の人達ともコミュニケーションを取る機会が生まれます。部署が変わることで他部署への理解が深まり部署間のミスを減らすことが出来ます。相互理解だけでなく、従業員の行える業務の幅も広がるメリットの多い制度です。

相互理解に取り組んでいるのは、株式会社ヤクルト本社です。ヤクルト本社では、ジョブローテーション制度を導入しており入社10年が経っている従業員は、3つの部署を経験していることになります。ジョブローテーションでは営業職から管理部に異動する人や、経理から海外出向を経験する人など従業員は様々な部署を経験します。ジョブローテーションによって様々な部署を経験する為、部署間でスムーズにコミュニケーションを取れる環境になっており、円滑に業務を行えています。

株式会社アカツキは、相互理解に取り組んでいる企業です。アカツキでは、企業が費用を負担し役員ランチを実施しています。普段業務に取り組む中で、従業員が役員と話す機会は殆どありません。その為、役員が何を考えているのか、従業員が何を思っているのかをお互いに知ることは簡単ではありません。アカツキでは役員と従業員が触れ合う場として、役員ランチを開催しています。役職が異なる人達がランチに参加することでお互いの考えを知ることが出来、会社の生産性向上に繋がっています。
 株式会社資生堂も相互理解に取り組んでいる企業の一つです。資生堂では、リバースメンターという制度を導入しています。通常のメンター制度では、経験豊富な従業員が若手従業員を指導するのが一般的です。しかし資生堂ではそのメンター制度をリバースしており、若手従業員が役員を指導するという方法を取っています。役員にとっては若手従業員の柔軟な考え方を知る貴重な機会となっており、固定観念に囚われない相互理解により、柔軟な考えを取り入れることで生産性向上も可能にしています。
株式会社資生堂も相互理解に取り組んでいる企業の一つです。資生堂では、リバースメンターという制度を導入しています。通常のメンター制度では、経験豊富な従業員が若手従業員を指導するのが一般的です。しかし資生堂ではそのメンター制度をリバースしており、若手従業員が役員を指導するという方法を取っています。役員にとっては若手従業員の柔軟な考え方を知る貴重な機会となっており、固定観念に囚われない相互理解により、柔軟な考えを取り入れることで生産性向上も可能にしています。
相互理解不足で陥る弊害や、相互理解を図るための方法について解説しました。相互理解が不足している事によって、部署間の連携ミスなど問題が発生しやすくなります。お互いの業務内容などをしっかりと理解することが出来れば、部署間の連携ミスが減り生産性の向上を見込むことが出来ます。相互理解により信頼関係が構築されている職場では、従業員が発言しやすく働きやすい環境になり離職率低下にも繋がります。相互理解を深める施策に取り組み、従業員が安心して働ける環境にしましょう。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。