記事更新日:2024年05月02日 | 初回公開日:2024年05月01日
用語集 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 グローバル用語解説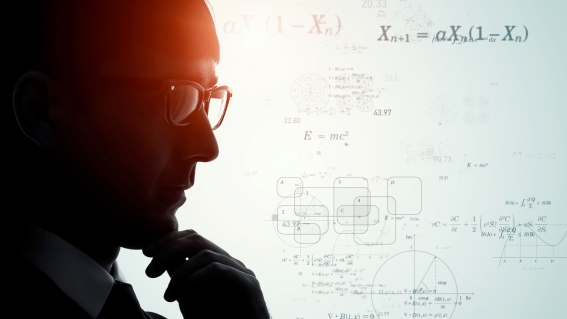
グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。

ハインリッヒの法則とは、事故に関する経験法則の一つです。人の生命が危険にさらされる様な労働災害を防ぐためには、一歩間違えれば大惨事に繋がりかねないヒヤリ・ハットに目を向けて問題が大きくなる前に対策を立てる事が重要です。ヒヤリ・ハットは同じ人間がもし330件の災害を起こした時、1件の重大災害と29件の軽傷を伴う災害とヒヤリ・ハットに該当する事案が300件起きていることが分かりました。このことから、「1:29:300の法則」とも呼ばれます。
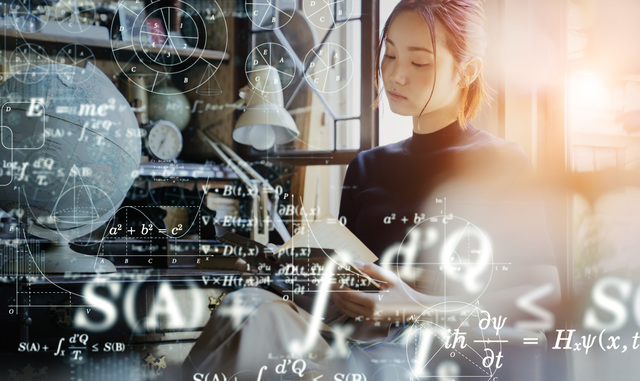
ハインリッヒ法則と似ている物にバードの法則があります。バードの法則は、1969年にフランク・バード氏によって提唱されたもので297社における175万件の事故報告を元にしている法則です。ハインリッヒの法則が5000件以上という件数なのに比べ、バードの法則は圧倒的に調査件数が多いのが特徴です。バードの法則ではリスクを考える時に、ハインリッヒの法則に加えて物損事故が加えられ1:10:30:600の比率でリスクを表します。

ハインリッヒの法則で重要なヒヤリ・ハットは、重大な災害や事故が起こる一歩手前の出来事です。ヒヤリ・ハットとは、怪我に繋がりそうな「ヒヤッとした」「ハッとした」出来事が起こってしまったものの、災害にまでは発展しなかった事案の事を指しています。ハインリッヒの法則では1件の重大災害の裏には300件のヒヤリ・ハットがあるとされています。これはヒヤリ・ハットを見つけることが出来なければ、1件の重大災害を防ぐことが出来ないとも言えます。

ヒヤリ・ハットが起こる理由は、設備の不具合やヒューマンエラーが原因です。設備の不具合には、設備の老朽化や整備不良などが該当し、定期的な点検や設備交換を行う事でヒヤリ・ハットを防ぐことが可能です。ヒューマンエラーによるヒヤリ・ハットは、作業の不慣れや焦り・疲労からくることが多いとされています。新入社員は業務に慣れておらず、リスク認識も甘いためヒヤリ・ハットが起こりやすくなります。またベテランも業務に慣れて油断が出ると、ヒヤリ・ハットに繋がります。

ハインリッヒの法則が発見された背景には、ハインリッヒが向上の労働災害についてリサーチしたところから始まっています。アメリカの損害保険会社の統計分析の専門家であったハーバート・ハインリッヒが1931年に発表した、「災害防止の科学的研究」にちなんで名づけられました。工場の労働災害を調べた際、重大事故が1件発生した際に背景には29件の軽い事故が発生し、ケガには至ってない物の未然の事故が300件発生していることを発見しました。

ハインリッヒの法則の具体例として、運輸交通業で起こったヒヤリ・ハットがあります。トラックから荷下ろしを運転手と作業者の二人掛かりでトラック広報に脚立を立てて作業を行っていました。作業終了後に運転手がトラックをバックしようとした際に、脚立を片付けていた作業者を引きそうになったという事案です。この事案では、運転手が既に脚立が片づけられていると思い込んでいた事が主な原因です。周囲の状況確認を怠らないことで、こういった事態を防ぐことが出来ます。

ハインリッヒの法則は、製造業でもヒヤリ・ハットが起こっています。製造工場で多く発生しているのが、ベルトコンベヤーの事故です。運搬用の大型ベルトコンベヤーの上を作業員が歩いた際に足を取られて転倒したり、ベルトコンベヤーを跨ごうとして転倒しそうになったりという事故が多く発生しています。どの場合においても、ベルトコンベヤーの上を歩かない・安全な通路を通って移動するといったルールが徹底されていない場合に起こっています。

建設業でのハインリッヒの法則の具体例は、建設中の足場でよく発生しています。建設現場では地上から高い場所に設置してある足場が設定されており、多くのヒヤリ・ハットが潜んでいます。足場の解体を行う際にバランスを崩して転落しそうになる・足場の板に段差がありその段差に足を取られて転倒しそうになるといった事案です。建設現場でヒヤリ・ハットを防ぐためには、安全帯の着用や足場を組み立てる際に段差を創らないようにするなど目視でしっかりと確認することが大切になります。

ハインリッヒの法則でよくある誤解は、世の中を前提にすることです。ハインリッヒの法則を授業員に説明する際に、「世の中では」「一つの会社では」と説明している人がいますが、これは正確ではありません。ハインリッヒの法則はあくまでも同じ人間が起こした事故についての比率を導き出したものです。そのため、企業規模が大きいと、従業員一人当たりのヒヤリ・ハットは少なくなると考えてしまいがちですが、あくまでも1人当たりの確立であることを認識しておきましょう。

ハインリッヒの法則は、300件のヒヤリ・ハットだと考えている人が多い点もよくある誤解です。1つの重大災害の背景には、300のヒヤリ・ハットが隠れているというような説明も正確ではありません。ハインリッヒの法則では、300件は傷害にならなかった無傷の事故件数を示しています。数え切れない程の不安全行動によって、たまたま無傷害として処理できた案件が300件で収まっているが30件の障害を伴う事故が起きる可能性があるという点が重要です。

ランダムな事故だと想定してしまう事も、ハインリッヒの法則でよく誤解されてしまう事です。ハインリッヒの法則で前提とされているのは、たまたま労働中に事故が発生するのではなく従業員が行ってしまっている不安全行動によって発生する類似の事故です。類似の事故が発生するに辺り、300件は無傷害ですが30件は傷害を伴う事故が発生し、1件は重大な傷害を伴う事件が発生するという可能性を示しています。1つの不安全行動が重大傷害に発生する可能性を示しています。
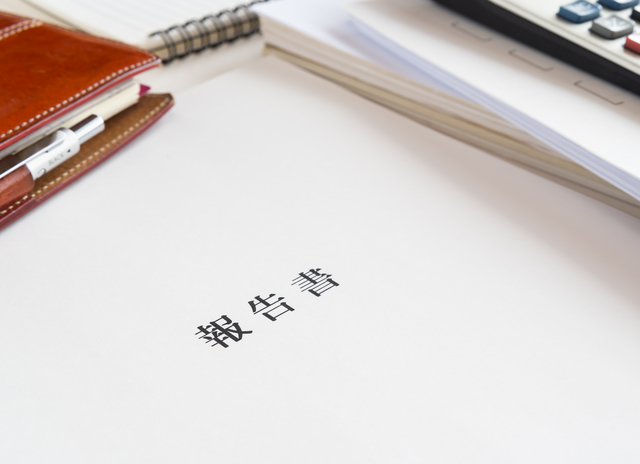
ハインリッヒの法則の活用方法は、ヒヤリ・ハット報告書の提出を義務付ける事です。職場内でハインリッヒの法則を上手く活用していくためには、ヒヤリ・ハットが起こった段階で状況の把握や情報収集を行う事が大切です。同じミスをしても、ヒヤリ・ハットであると考えるかは人によって差が出るためまずは危険性の高い場所や作業の洗い出しから行いましょう。記名制の報告書は受け入れにくい人もいるため、無記名のなるべく簡潔な報告書を使いましょう。

ハインリッヒの法則の重要性を理解してもらうためには、安全研修を行いましょう。製造業などではヒヤリ・ハットが起こる確率が高いため、ハインリッヒの法則が浸透している場合が多いですが安全活動を行ったことのない人にとっては初めて聞く言葉です。耳にしたことはあっても内容までは理解していないという人もいるため、安全研修は必須事項です。安全研修を受ける事で、ハインリッヒの法則への理解やヒヤリ・ハットに対して同じ認識を持つことが出来ます。

ヒヤリ・ハットに対して議論する場を設ける事も、ハインリッヒの法則の活用方法の一つです。実際に企業内で起きたヒヤリ・ハットや、関連業界の事例を元にしてヒヤリ・ハットが発生した原因や対策を話し合う場を定期的に設けるようにしましょう。定期的に議論する場を設ける事によって、従業員の安全に対しての意識を高めることが出来ます。毎回同じメンバーで議論すると、形骸化してしまいがちになるため違うメンバーを選出することなど工夫が必要です。

ハインリッヒの法則を活用し、安全大会を実施する方法もあります。従業員全員が揃う場で、ヒヤリ・ハットの事例や実体験・防止策の共有を行い、発表や報告が多かった従業員の表彰などを実施しましょう。安全大会は従業員を災害から守ることを目的として実施されており、建設業や製造業では定期的に実施されています。内容は企業によって異なりますが、安全講和や対策訓練・表彰式を行う事が一般的です。従業員が全員参加することで、安全の意識向上の役目を果たしています。

職場内でヒヤリ・ハットを教諭する仕組みを整えておきましょう。ヒヤリ・ハットが起こった際に報告書を提出するようにフローを創っていても、起こった内容が従業員に共有される仕組みが出来ていなければ予防に繋げられないため意味がありません。同じような事態を発生させないためにも、起こったヒヤリ・ハットは社内で共有する事が大切です。共有方法としては、企業により異なりますが掲示板で共有・メールで展開するなど様々な方法があります。

ハインリッヒの法則を学んだ上で企業が取り組める対策は、危険予知訓練を行う事です。ハインリッヒの法則の理解を進めた上で、従業員の安全意識をさらに高めるためには棄権予知訓練がおすすめです。危険予知訓練とは、普段の業務の中に潜んでいる危険を感じ取り問題を解決する力を高めるための訓練です。危険予知訓練を導入することで、普段からヒヤリ・ハットに対する感受性を高められるだけでなく職業倫理の向上などにも繋げる事が出来ます。

ハインリッヒの法則の具体例や、活用する方法などについて解説しました。ハインリッヒの法則は重大な労働災害の裏には目に見えないヒヤリ・ハットが数多く潜んでいることを示している法則です。安全活動を行っている企業では当たり前のように使われていますが、従業員全員が重要性を理解しているとは限りません。安全意識を高めるためには、ハインリッヒの法則についてしっかり理解してもらいましょう。ハインリッヒの法則を活用して事故防止に努めましょう。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。