記事更新日:2022年01月14日 | 初回公開日:2022年01月04日
グローバル用語解説 人事・労務お役立ち情報 グローバル経済 グローバル用語解説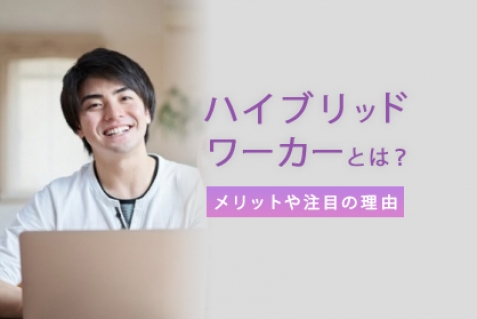

「ハイブリッドワーカー」とは、空いた時間で収入を伴うクリエイティブな活動をしている人のこと。会社勤めをしながら、空いた時間や休日にはやりたいことを仕事として、自己実現のために活動するという副業スタイルです。仕事とやりたいことを切り離すことで、経済面で安定しながら夢を追いかけることができる働き方として注目されています。ハイブリッドワーカーとしての働き方は、本業・副業双方で得た経験を活かしていくことができるという特徴があります。

最近では、ハイブリッドワーカーの数は増加傾向にあります。増加の背景には、SNSの普及が大きく関わっています。TwitterなどSNSの普及によって、自分の作品を発信する場が増えました。発信する場が増えたことで、企業の目に留まりやすくなり、作品が書籍化・記事化するなどチャンスをつかみやすい環境になったのです。バズツイートが企業の力によって拡散され、自身のブログのアクセス数が上がり収入につながったという例もあります。多くのクリエイターにとってSNSは非常に重要なツールになっています。

SNSの普及は、ハイブリッドワーカーに注目が集まる背景にも関係しています。SNSに作品を投稿することで有名になったクリエイターの中には、自身の仕事のことも含めた日常をSNSに発信している人もいます。サラリーマン兼漫画家、薬剤師兼ミュージシャンなど意外な組み合わせで仕事をしているハイブリッドワーカーの日常からは、充実した生活がうかがえます。SNSは作品の発信だけでなく、ハイブリッドワーカーという働き方を知る機会ともなっているのです。

働き方が多様化している現代で、ハイブリッドワーカーは注目を集めています。なぜなら、ハイブリッドワークは単なる副業ではなく、自身の好きなことをして収入を得るという特徴があり、現代の社会人の心を打つものとなっているからです。本業で経済面は安定しながらも、好きなことを仕事にできて夢を追い続けることができます。SNSの普及によって発信する場にも恵まれるため、チャンスも十分にあります。ハイブリッドワーカーは、働き方が多様化している現代で注目を集める働き方の一つとなっています。

働き方の多様化から、副業に興味を持つ人が増えたことも、ハイブリッドワーカーが注目される理由の一つです。終身雇用は今や古い文化となり、会社員だけで収入を得ることに不安を感じる人が多くなりました。そのことから副業に関心を持つ人が増えていき、副業OKの企業も出始めています。副業に寛容な時代になりつつある現代において、ハイブリッドワーカーは、収入を得つつもワークライフバランスも叶えられる働き方として注目されています。

ハイブリッドワーカーは、社員・企業双方にとってメリットがあります。一つは、社員のストレスがたまりにくいこと。会社勤めは、上司部下の関係においてコミュニケーションが発生するため、ストレスをゼロにすることは難しいものです。ハイブリッドワーカーの場合、就業時間外で好きなことを副業としているため、もう一つの仕事でストレス発散ができているのです。ストレス発散の機会としてハイブリッドワークを推奨することは、社員の早期退職の防止にもつながっていきます。

ハイブリッドワーカーは、本業へのモチベーションが高い傾向にあります。例えば、本業での経験を元にブログや記事、漫画などを書く場合、実体験があるからこそ作品に多くの反響が得られます。また、副業で得た知識やスキルが本業に活かされることもあります。ハイブリッドワークは、ストレス発散もできて、本業・副業双方にとって相乗効果が期待できるのです。相乗効果を実感することで、本業へのモチベーションの向上につながります。

自分で稼ぐことができるハイブリッドワーカーは、経済面で余裕が生まれます。社員の経済面安定がもたらす企業へのメリットは、給与を理由にした早期退職を防止できることです。ハイブリッドワーカーは、収入を企業だけに依存しないため、給与額を問わず一つの企業で長く就業できる傾向があります。もちろん、副業をしているからといって社員の昇給機会をなくしてはいけません。しかし、企業にとっては、負担を増やすことなく早期退職のリスクを減らせることが大きなメリットと言えるでしょう。

ハイブリッドワーカーは作業の効率が上がりやすい傾向にあります。副業は、本業よりも少ない時間で仕事をしているため、作業効率が求められます。そんな副業での働き方が本業にも活かされ、少ない時間でも成果が上がるような作業効率が身につくのです。また、副業ではタスク管理や利益計算などすべて自身で行う必要があるため、マネジメント力やプロ意識が育ちます。本業以外で自ら成長することができ、ひいては人材育成にもつながっていくのです。

働き方の多様化が進む中、副業を推奨している企業はまだごくわずか。そんな中、副業を推奨(または副業を禁止していない)企業へは、社員の満足度が高くなる傾向にあります。現代の働き方に対応しようとしている企業努力や、自分のやりたいことを応援してくれる姿勢が見える点から、企業への満足度が高くなります。企業への満足度が高い社員は、本業へのモチベーションも向上し、早期退職の防止にもつながります。また、本業では身につかないスキルを持った社員から新たなビジネスチャンスが生まれることもあります。

ハイブリッドワーカーにはデメリットもあります。まず一つは、社員の健康管理が難しくなることです。ハイブリッドワーカーは、就業後の時間や休みの日を使って仕事をしています。そのため、副業を禁止している企業と比べ、社員の健康管理が難しくなります。社員の健康管理は会社の義務であることが労働契約法で定められました。しかし、企業の管理が及ぶのは本業の仕事の範囲内なので、副業時間まで管理することができません。副業による健康被害においては責任の所在があいまいになり、健康管理が難しくなってしまいます。

二つ目のリスクは、情報漏洩などのリスクがあることです。本業での肩書や業務内容を活かしてブログなどを書く場合、本業で知りえた情報をブログに書きこんでしまうといったケースです。副業で様々な顧客と接点を持つ機会があれば、本業に関わる人の連絡先や個人情報等が漏洩するケースもあります。情報漏洩は、企業にとって大きなリスクになるため、社員の副業においては注意しておきたいポイントです。社員と機密情報に関する誓約書や、使用機器についての誓約書などを結ぶといった対策が必要です。

ハイブリッドワーカーとして副業を認める場合、企業としても体制を見直す必要があります。まずは、就業規則の見直しです。社員の副業を認める場合は、就業規則の副業・兼業の項目に、副業を許可しているという旨を記載します。副業をする場合の申請や、副業を禁止・抑制することができるケースについても明確に定めましょう。就業規則は、企業と社員が就業時間内でトラブルなく働くための規則です。副業禁止の項目を残したまま社員の副業が発覚した場合、のちにトラブルに発展する可能性もありますので、就業規則でしっかりとルールを定めておくことが重要です。

就業規則で副業に関するルールを定めたら、社員にはその内容を共有します。副業の申請フローや、不許可となるケース、副業においての注意点など、就業規則で定めていない細かいルールについては、別途ガイドラインを設けましょう。企業が副業を認めても、社員がそのことを知らない場合、本当の意味で副業が認められていることになりません。前述の通り、就業規則やルールについては、変更があれば社員にも周知し、企業と社員で共通認識をしておくことが重要です。

副業は、業務時間外で行われるとはいえ、労働時間をある程度把握しておく必要があります。労働基準法では、「本業と副業の労働時間は通算される」とあり、本業と副業の通算労働時間が、労働基準を超える場合は残業代の支払い義務が生じます。多くの場合、残業の支払い義務が生じるのは後から契約した副業側になりますが、本業側で残業指示を出して労働基準を超える場合は本業側の負担になります。残業代の支払いが発生する可能性がある事から、本業・副業での労働時間は、本業企業側も把握できる体制を構築することが必要です。

ハイブリッドワーカーの代表的な事例を二つご紹介します。まず一つは、サラリーマンと漫画家の兼業。漫画家田中圭一さんは、玩具メーカーの営業マンとして会社勤めしながら、土日は連載漫画を描いていました。玩具メーカーを退職後、ゲーム開発やソフトウェア開発の企業に転職し、現在は漫画コースの大学教授として勤めています。田中圭一さんは、営業マンとしてのスキルが漫画の仕事がない時期を助け、漫画家だからこそお絵かきソフトの発案ができたとのことです。本業と副業の相乗効果が出ているモデルケースと言えるでしょう。

もう一つの事例は、薬剤師とミュージシャンを兼業している例です。ケツメイシのRYOさんは、薬剤師資格を持っており、製薬会社の営業や薬剤師として勤めながら、休みの時間を使って音楽活動をしていたそうです。兼業でミュージシャンを目指すことに対し、周囲からは中途半端だと言われてしまうこともあったそうです。しかしRYOさんは音楽活動は本業以外の時間を使うことを選びました。プロのミュージシャンとして成功した後も、以前勤めていた薬局にはたまに顔を出すこともあるそうです。

今回の記事では、ハイブリッドワーカーについてご紹介しました。働き方が多様化する現代では、副業にも関心が高まっています。そんな中、企業としても社員の働き方の見直しが求められ、ハイブリッドワーカーの特性についても理解が必要です。副業推進は、少なからずリスクを伴うケースもあります。しかし、本業と副業の相乗効果で、本業において人材育成や早期退職の防止など、多くのメリットがあります。今回ご紹介した内容を含め、ハイブリッドワーカーへの理解を深めることが、副業推進の始まりです。ハイブリッドワーカーへの理解を深めた上で、企業・社員ともに気持ちよく働けるような副業の体制づくりを検討してください。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。